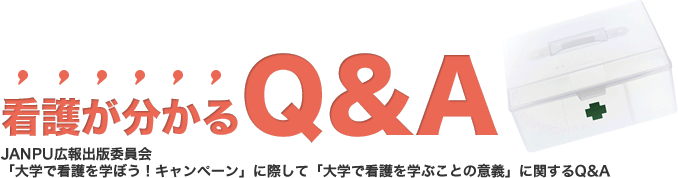-
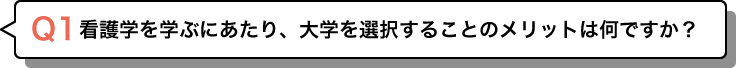
看護師や保健師、助産師の国家試験を受けるために必要なカリキュラムは、厚生労働省が規定している
(保健師助産師看護師学校養成所指定規則)ので、大学においてもその内容と時間数は満たすことが求められます。
こうした中でも4年制大学で看護を学ぶメリットには、次の6つの点を挙げておきたいと思います。・ 一般教養科目を学習する時間を持つことができる
・ 休暇を利用して海外留学や研修などの経験を豊かにすることができる
・ 多様な専門分野を深めている教員から教わることができる
・ キャリアアップのために大学院(修士・博士課程)に進学できる。
・ 国家試験合格率は、専門学校、短大に比べて高い(2012年度の合格率は表をご覧下さい)
・ 学歴は大学卒となる -
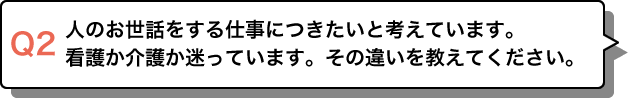
介護は主として高齢者を中心に、身体機能が低下した状態にある人を生活の視点から見て「生きる」を支えます。
看護の対象者は年齢に関係なく、胎児の健康管理から子ども、おとな、高齢者、あるいは軽い病気から重い病気まですべての人を対象として、病気と治療と生活といった多面的な視点から「生きる」を支える仕事です。
このように看護は医療専門職とされていますが、医療に留まらず、介護や福祉、保健といった幅広い知識と技術を身につけて社会の変化に対応しながら、人々がより良く「生きる」ことを実現しようとしています。
現在、介護の実践家の間では、対象となる人の健康問題がわからないと質の高い介護ができないという意見が出ています。
例えば、食事を助けるケアでは、食べる手伝いをするだけでなく、食べ物を飲み込めないとか、お箸が使えないという身体機能の低下が、その人それぞれにどのような病気の影響からくるものか、治療や訓練でどこまで適応していけるのかを検討しなければなりません。
対象となる人、それを取り巻く家族、医師、理学療法士、保健師など様々な人と共に、当事者が「生きる」道を作っていくのを助けるのが看護師です。大学で看護を学ぶことで、その役割を担うために必要な様々な分野の知識を効率的に習得できると思います。 -
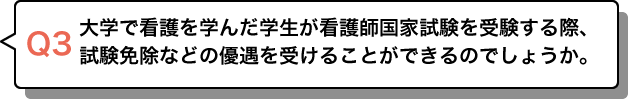
看護系大学を卒業して得られるのは、看護師等の国家試験受験資格です。
国家試験は、卒業した学校の種類によって異なる扱いはなく、みな同じ試験を受験することになります。
なお看護系大学のなかには、卒業時に看護師国家試験受験資格だけでなく、保健師あるいは助産師国家試験受験資格も得られる大学があります。表(大学一覧、大学院一覧)に大学別一覧を掲載しましたのでご覧下さい。 -
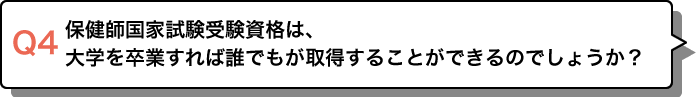
大学によって異なりますので、表(大学一覧、大学院一覧)をご覧下さい。
大きく分けて、4年間の学部教育の中で学生全員が保健師国家試験受験資格を取得するために必要な単位を履修することができる大学と、選択した学生のみが4年間の中で履修することができる大学と、専攻科を設けて必要な科目を履修できるコースを別にしている大学、そして、大学院で保健師になるために必要な単位を履修するようにしている大学の4種類があります。
また、看護系大学を卒業した後に、保健師学校養成所に入学することも可能です。 -
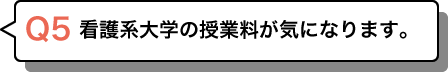
看護系大学も国立、公立、私立と分けることができ、授業料はそれぞれ異なります。
国立大学の授業料は他学部と同じですので、初年度は約80万円程度を納めることになります。
私立は大学ごとに異なります。看護大学・専門学校受験ナビ(2013年4月2日検索)によると、初年度の納入金は、140万円から240万円(2011年度実績)が参考値となっています。
なお初年度納入金には、入学金、授業料、施設設備費など大学によって決められた費目が含まれています。 -
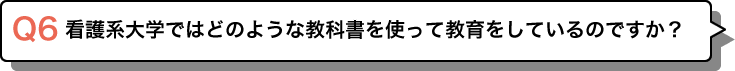
看護学を学ぶための教科書は各種の関連する出版社からたくさん出されていますが、大学ではこれらの教科書を使用する義務はありません。
科目を担当する教員の自由な発想で教材を選び作成することになります。
大学の教員は、そもそもの元となるデータや研究論文などから引用しながら、学生が看護をよく学ぶことができるよう、
最新の根拠に基づいた教材を開発しています。 -
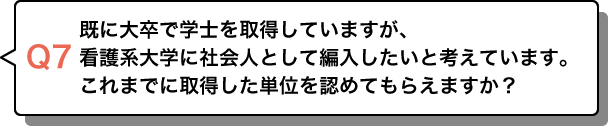
社会人入学を受け入れている看護系大学については表(大学一覧、大学院一覧)をご覧下さい。
近年の社会の構造的変化と医療に対するニーズの増加などから、看護系大学に編入することを希望する方は増えています。
単に看護師資格を取ることを目指すのではなく、新しい社会ニーズに対応できる深くて柔軟な看護を学ぶためにも大学を選択することをお勧めします。既に卒業した大学での単位については、ほとんどの大学では認めているようですが、詳しくは個々の大学にお尋ね下さい。