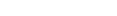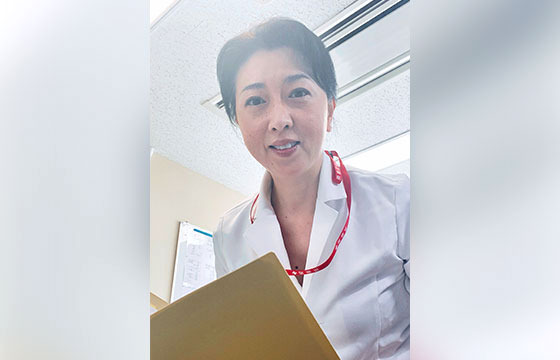
- 獨協医科大学 看護学部
- 須坂 洋子
東京都立大学人文学部心理・教育学科を卒業後、東京都立青梅看護専門学校に進学し、看護師免許を取得。東京都立神経病院で勤務をする(脳神経内科病棟)。勤務を継続しながら、聖路加看護大学(現 聖路加国際大学)大学院博士前期課程に進学し、2017年に遺伝看護専門看護師となる。獨協医科大学医学部特任講師を経て、2022年から獨協医科大学看護学部(現職)。現在、新潟大学保健学研究科博士後期課程に在学中。遺伝看護の研究を続けている。
動機はともかく、看護師を継続している私からのメッセージ
みなさんには、将来の夢がありますか? 私は、10代の頃、将来の夢はありませんでした。なりたい職業はなく、働くことは面倒だと思っていました。そんな私が看護師として夜勤もこなしながら働き、そして現在は看護を教える大学教員という仕事に就いています。
私がなぜ看護師になったかというと、生きていくためにはお金が必要だからです。看護師を選んだ理由は、「女性でも長く働くことができる」「就職率100%」という理由からでした。私は一般大学を卒業したのですが、当時は、女性の就職は難しい時代でした。男子学生と比較して、女子学生に対する求人案内はとても少なく、優秀なクラスメイトでさえ就職に苦労をしていました。たまたま、大卒後に看護学校に進学するクラスメイトがいて、私もそれを真似することにしました。つまり私は、女性の就職難という時代背景があり、さらに「特にやりたい仕事もない」という理由で、看護師になったと言えます。
「就職率100%」という理由で看護の仕事を選んだというのは、動機としては褒められたものではないかもしれません。そもそも私は、なにをするにも気が利かず、人付き合いも苦手です。看護師として働き始めても、自然に体が動いたり、自然に患者さんに言葉をかけたりができず、最初の3年間は怒られてばかりでした。ですから、1つ1つ、先輩たちの看護を見ながら学習していく必要がありました。先輩たちの看護を見て、(こんな風にして患者さんの相談にのるんだな)などと、先輩たちのすばらしさに感動していました。
人が人を助ける看護という仕事は、1つの動作にさまざまな意味や効果があり、奥が深いです。特に看護師は、手や身体で患者さんのケアをする場面が多いです。医療が高度化するなかで、脈々と行われてきたその原始的なスタイルは、つい見とれてしまう魅力があります。
看護師になって1年目の夏過ぎでしょうか、初めて一人の患者さんを受け持つ機会がやってきました。その患者さんは、診断目的で入院をし、様々な検査を受けていました。私は患者さんの力になりたくて、積極的に検査の介助をしたり、症状の観察をしたり、日常生活の援助をしたりしました。そして、病名を告知される日が来ました。私は受け持ち看護師の役割を果たそうと、その告知の席に同席しました。その席で、主治医が患者さんに、遺伝性疾患であることを告知しました。私は病名を聞いて、(そんなに症状が重い病気でなくて良かったな)と、少し安心しました。すると患者さんが突然、声をあげて泣き始めたのです。私は驚きました。患者さんは泣きながら、「私はどうなってもいいけれど、子どもや孫に病気が遺伝していたら、私はどうしたらいいのですか」と言いました。私は患者さんになんとこたえたらよいか、まったくわかりませんでした。患者さんは自分の病気を心配しているのではなく、「遺伝」という事象を心配し、苦しんでいたからです。
家に帰って教科書を見ても、「遺伝」ということで悩む人への看護は書かれていませんでした。先輩に聞いても、明確なこたえは返ってきませんでした。私は(あんなに人が泣く「遺伝」とは、いったいなんだろうか)と疑問に思いました。その疑問を解消しようと調べているうちに、「遺伝看護」という領域があることを知りました。まだ日本ではあまり知られていなかった領域です。私は、教科書に書かれていないので、学会や研修会に参加して学びを深めていきました。さらに勉強を進めていくうちに「遺伝看護専門看護師ができる」という話を聞きました。私は遺伝看護を広めていきたいと考えていたので、専門看護師になろうと決意しました。本屋に行って英語の参考書を買い、忘れていた英語の勉強をし直して、看護師7年目に大学院に進学し、無事に遺伝看護専門看護師の第1期生に認定されました。
大学教員に転身したのは、遺伝看護を広く伝えたいと考えたからです。まだ看護師免許を持っていない学生は、看護に対する「諦め」がありません。私だったら(どうせ忙しくてできない)(師長さんが許してくれないだろう)などと、諦めるための言い訳がたくさん出てくるのに、学生はそんな言い訳は一切言わないのです。学生は、できる限りのことを患者さんやご家族にしたいと考えている人が多いです。学生に遺伝看護の話をすると、すぐに「やってみようと思います」と具体的な看護計画が出てきます。私は、限界をひかないで看護を考える学生の姿勢に、日々、感銘を受けています。
看護は「人が人を助ける」という、とてもシンプルで根源的な営みに、まっすぐ焦点を当てた学問であり、実践です。いま目指している私の研究テーマは、「地域で暮らす人々に必要な遺伝看護はなにか、地域で暮らす人々に遺伝看護の実践をどのように届けるか」というものです。病院の中だけで看護を考えていると、人々の「生きる」という営みからどんどん乖離してきて、結局は患者さんや家族のニーズにこたえられていない、病院の価値観ややり方を押し付けている、と感じるようになりました。
遺伝看護は、遺伝医療に対する看護を開発し、実践していきます。遺伝医療は高度な専門病院で行われるもの、というイメージがあるかと思います。しかし今や遺伝医療は、一般診療の場で広く用いられる時代に入りました。その時代の流れにあって、遺伝看護も、地域で暮らす人々のニーズに合った看護を開発し、実践できるようにしていく必要があると考えます。私は、看護教育の中にある「病院」と「在宅」の間の垣根を低くして、看護の「生活を守る」という側面を、より人々のニーズに合ったものにしていきたいと考えています。
人が人を助けようとする看護という営みは、私にとって、遺伝医療と同じくらい「最先端のテクノロジー」です。看護はまだまだ発展していく余地があります。私は看護が苦手な看護師のままですが、看護についての興味は尽きる気がしません。それはひとえに、看護にまっすぐな学生が私に看護を教えてくれるからです。これを読んでいるみなさんと、ともに看護について学び、話し合うことができる日を楽しみにしています。