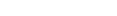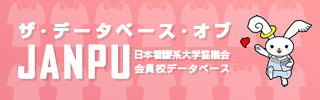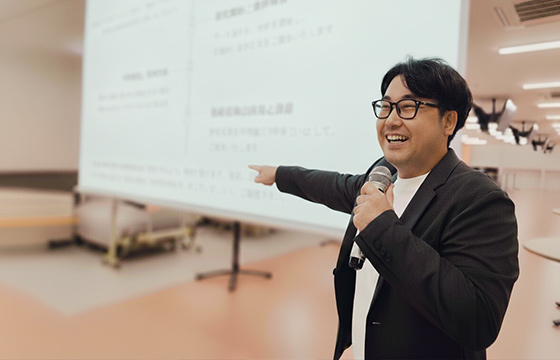
- 鹿児島国際大学 看護学部 看護学科 在宅看護学分野
- 水迫 友和
鹿児島市立高等看護学校を卒業後、鹿児島大学病院霧島リハビリテーションセンターに看護師として勤務。その後、2012年に脳卒中リハビリテーション看護認定看護師の認定を受ける。2017年より教育専従看護師として院内の教育に携わる。2019年に鹿児島大学医歯学総合研究科修士課程へ進学し、2021年に修了。2023年より兵庫県立大学大学院情報科学研究科博士後期課程に進学し、現職に至る。
看護×AIで鹿児島の課題を解決する
鹿児島県内の看護学校を卒業してから、私は鹿児島大学病院のリハビリテーション病棟に配属されました。そこで出会ったのが、脳卒中看護とリハビリテーション看護です。麻痺のある手をゆっくりと動かそうとする患者、うまく言葉を話せなくても目で必死に何かを伝えようとする表情。その一つ一つを支えることに、看護の本質が詰まっていると感じました。
私は、看護師としてのキャリアを重ね、やがて認定看護師の資格を取得し、脳卒中看護の実践を重ねてきました。しかし、経験を重ね臨床で働くほど、大きな課題に直面しました。それは、ベッドサイドで患者と向き合いたいのに、記録や情報収集に追われ、肝心のケアの時間が削られていく。「もっとベッドサイドでケアができたら」──その思いは日に日に強くなった気がします。
どうすれば、ケア時間を増やせるのか。答えを模索する中で、私は医療情報やAIという領域に着目しました。記録の効率化、リスク予測、ケアプランの最適化。AIの力で、看護師が本来向き合うべき”人”に、もっと時間を使えるはずだ。そう確信して、大学院への進学を決めました。現在は兵庫県立大学大学院情報科学研究科の博士後期課程に在籍し、看護×AIの研究に取り組んでいます。
研究を進める中で、次第に「この知見を、どう現場に活かすか」という問いが浮かんできました。論文を書くだけでは足りない。次世代の看護師を育て、地域の課題に向き合う人材を輩出すること。それが、私の学びを最も活かせる道ではないか。そんな時、鹿児島国際大学看護学部学部長よりお声かけいただき「鹿児島のために頑張ろう」──その言葉が、私の中で強く響きました。高齢化の進む離島、医療資源の限られた中山間地域。鹿児島が抱える課題と、私が研究として取り組んでいるAIの可能性が、ここで重なった気がしました。迷いは全くなく教員として、鹿児島で学生と共に歩むことを決意しました。
講義では脳卒中看護やリハビリテーション看護の魅力を伝えつつ、AIを用いた看護研究の可能性についても語っています。「看護とAIって、つながるんですね」と目を輝かせる学生もいれば、「データだけじゃ患者さんは見えない」と鋭く問いかける学生もいます。そんな、自分にはない感性や見えていなかった視点に触れるたび、私自身が学ばされています。教育とは一方通行ではないことを最近、強く感じるようになりました。学生の成長が、私の研究や教員としての成長を「UP
DATE」してくれています。
先日、実習先で、ある学生が「患者さんの表情がいつもと違った気がして、それが気になって、看護師と話し合ってきました」と、報告してくれました。その学生が感じた気づきを看護師が拾い上げ、チーム全体で検討した結果、患者の本当の想いにそった対応ができたという報告でした。AIなら数値の異常を検知できるかもしれません。しかし、患者のちょっとした変化を「何か違う」と感じ取るのは、やはり看護師にしかできないことです。私は、AIと看護が対立するとは思っていません。AIが記録や分析を支え、看護師が五感と経験で患者を観る。その共鳴による相乗効果が、看護を深めるのだと考えています。
私が今、最も力を注ぎたいことは、看護×AIで鹿児島の課題を解決することです。高齢化率の高い離島や中山間地域では、限られた人員で多くの患者や住民を支えなければなりません。遠隔モニタリングや予測モデルを活用すれば、早期介入が可能になり、在宅医療の質も向上する。鹿児島の地域特性に即した看護DXに取り組んでいきたいです。
週末、私はよく鹿児島ユナイテッドFCの試合を見に行きます。スタジアムで歌う応援歌の一節が、いつも胸に響き私を奮い立たせます。「今日もこの場所で 共に戦う 俺らは歌うのさ
鹿児島のために」。この歌詞は、私にとって単なる応援歌以上の意味を持っています。医療も、サッカーも、地域と共にある。一人では成し遂げられないことを、仲間と、地域と、共に前へ進める。そんな在り方が、私の原点だと考えています。
教員となった今も、私の中にあるのは「原点であるベッドサイドに還りたい」という思いです。それは物理的にベッドサイドに戻るという意味ではなく、看護の本質に立ち返るということ。AIや情報技術は、その手段に過ぎません。最終的に目指すのは、看護師が患者のそばで、もっと密に、もっと深く関わり続けられることです。
そのために、患者の本当の想いに気づき対応できる看護職を育成する教育、そして看護×AIの研究を深め、生まれ育った鹿児島の力になれるよう、臨床と教育をつないでいきたいです。